# ノクチルが羨ましい
この記事は2020年7月1日よりアイドルマスターシャイニーカラーズで開催されたイベント「天塵」に関する妄言です。今回は個人に対する言及はしません
# 僕らにもいつだってと言える時がある
# 郷愁
同級生、友達、幼馴染。誰だって以前は、あるいは今、もしかするとこれから先、一度は経験したことがあるだろう。本当に経験が無かったとしても漫画やゲームで似たような概念に触れたことはあるだろう。僕だってこれらの言葉に対する印象の半分ぐらいは主にギャルゲーからの輸入品である。そしてそれらは基本的には非常に得難いもので、また大変にありがたい存在である。だからこそ、そこから得られる体験は何物にも代え難く、増えれば嬉しく、失えば悲しむ。また更に困ったことに、体験は増えれば増えるほどに後悔を生む。それも、単純な失敗に対してだけはなく、楽しかって、嬉しかった、笑えた、全ての行為に対して。「もっと」という欲望は、下手をすれば楽しかった体験にこそ歯止めの効かない麻薬であるから。
僕たちはそんな思いをいつだって抱えながら、自分に出来る範囲の日々を過ごしていく(「いつだって僕らは」はそんな惰性的な意味の歌では無いと思うのでこのフレーズと重ね合わせないように)。
浅倉透のようなリーダーシップを発揮してみんなの先頭に立ってみたり、場を引っ掻き回してみたり集団を取りまとめてみたり。
樋口円香のようにシニカルさを真似して抑え役に回ってみたり、頼りないリーダーを補佐してみたり、対抗意識を燃やしてみたり。
福丸小糸のような後ろを歩くポジションで、もしかすると集団に対して負い目があって、勝手に遠慮してみたり、関係に悩んで、いざというところではそんなこと誰も気にしていなかったり。
市川雛菜のように積極さと強引さを発揮し、いつの間にか集団を引っ張るようになっていたり、いろんな出来事を呼び込んだこともあったり。
彼女たちほど派手でなくてもいい。キラキラしていなくてもいい。僕たちが今まで重ねてきた経験にはきっと似たようなことがあって、当然それは誰か一人のポジションのものではない。集団によって違い、その中でも役割は毎日のように変化し、それぞれが出来る範囲で積み重なっていく。
そうやっている内に溜まっていった後悔を吹き飛ばし、突き抜けていく存在。それがノクチルだった。彼女たちはどこまでも純粋に、そして遠慮することなく全力で「幼馴染」をしている。僕たちが積み重ねてきたものに少しの共感と大きな羨望を与え、しょうもない鬱憤を吹き飛ばして走り去っていく。それが本当に痛快で、明日を迎える元気をくれるから。彼女たちにはこれからもずっと「幼馴染」であってほしいと思うのだ。
# 既定の幼馴染
「天塵」は主に2つの話を見せてくれる。アイドルになる前のノクチルと、アイドルになった後のノクチルの話だ。そして前半の話は非常に単純な構造である。我等友情永遠不滅最強幼馴染に喧嘩を売ったイケてない大人に天誅を下すツーカイでスカッとする話。「イエーイ」というやつである(この「イエーイ」とは意味が違うだろという話はぜひ歓迎する)。

海に行く約束をした、みんなで車を買おうと言った、一緒にレッスンをした、ちょっとした隠し事を共有した、道具の使い回しをした、横柄な大人に逆らった。 どれかは僕たちもやろうとしたかもしれない、一つはやったかもしれない。似たような経験なら全部したかもしれない。彼女たちはそんな、何でも無い出来事の一つ一つを全力で過ごしていく。リーダー格にカリスマがあるから、ちょうど気の合う4人だから、花の女子高生だから、何が理由なのかは分からないが、それでもその瞬間を駆け抜けていく彼女たちに、溢れんばかりの光を思うのだ。
# 幼馴染の再定義
ところで、そんな彼女たちは、現状ではもっとも大きいコミュニティである「社会」に働きかける力を持たない、あくまで学生の身である。ところが、アイドルという仕事も持っている。だからこそ生配信という大きな場で大立ち回りが出来てしまったし、それにより大きな波紋を呼んだが、結局は彼女たち自身に報いが跳ね返ってきただけで、それ以外は変わらず流れていく(いや283プロの責任問題じゃねーのか、といった話は作中でも出なかったので気にしないことにする)。彼女たち4人自身の中では最強に刺激的だった日常も、もっと大きな枠組みから見れば何の影響もない、それこそまさしく透明な何かでしか無かったのだ。
当然、彼女たちはもう一度問われることになる。自分たちのあり方を。自分たちを認めない傲慢な大人たちを前に、その横暴から身を離すか、それとももう一度立ち向かうかを。
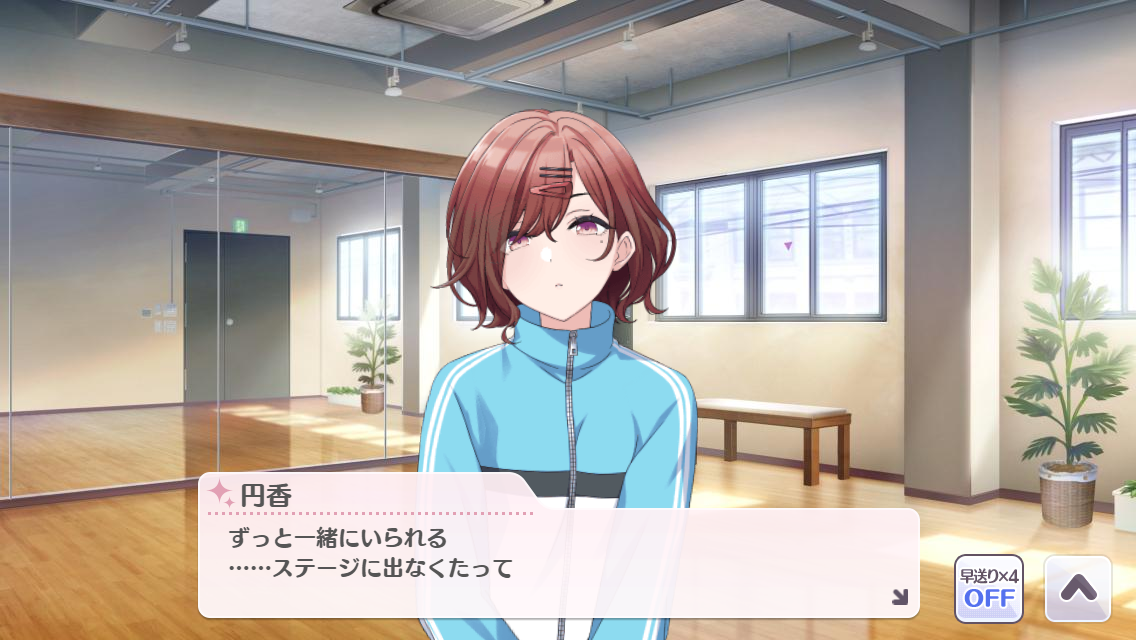
第6話『海』にて、プロデューサーが藁から掴み取ってきた小さな営業案件に対するノクチル各人の対応は、各個人の思いよりも、それぞれが4人のことを考えた時の振る舞いに見えたが、結局彼女たちはこの案件を受けることになる。彼女たちは退かなかった、恐れなかった。乱暴な大人の勝手に敢然と立ち向かい、報復を受けても折れず、再び掴みかかろうとしている。自分たちの存在を認めさせるためか、負けたままではいられないからか、それそのものに楽しさを見出したか、彼女たちは、彼女たちであり続けるためにアイドルという武器を取り立ち上がった。
そう、手段としてのアイドル。今回のイベントシナリオでは一貫して彼女たちのアイドルそのものへの感情を見せることはされず、4人が幼馴染であり続けるための選択肢の一つとしてアイドルというものが存在している。これは過去のユニットシナリオではあまり描かれてこなかったものであり、アイドルとしてのノクチルというよりも、ノクチルはアイドル足り得るか、という話として感じられる。
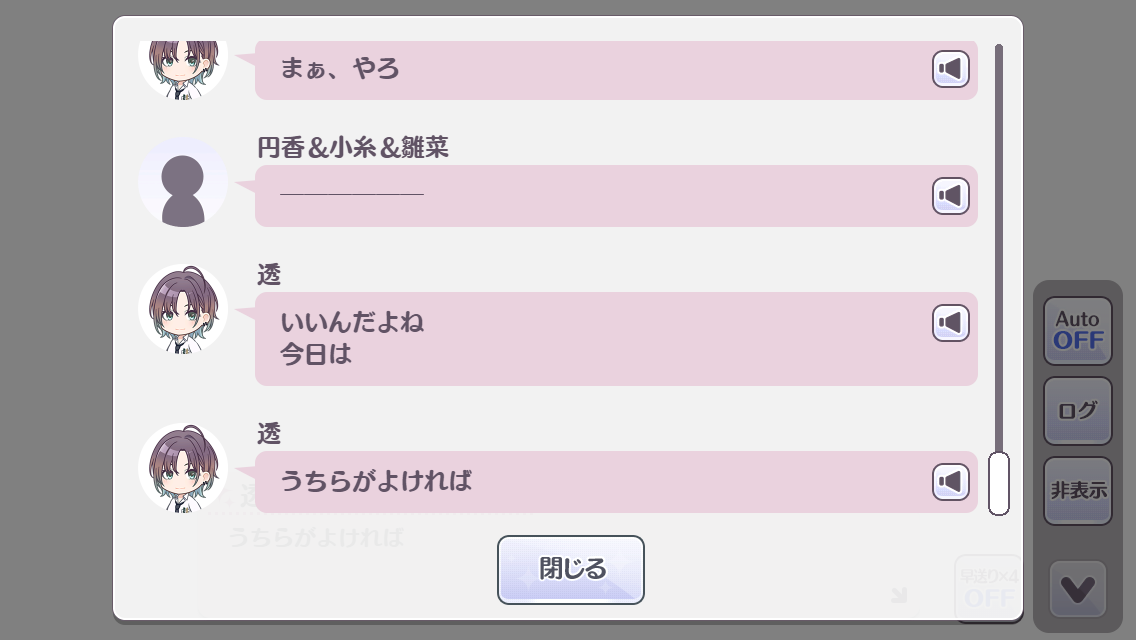
尤も、作中でプロデューサーが彼女たちの魅力について、そこにあるがままの彼女たちの輝きを見ている以上はそういうことなんだと思う。ノクチルはアイドルユニットありきで集まった4人ではない。彼女たちにはもっと以前からの強い結びつきがあり、その結びつきはアイドル足り得るか、彼女たちがこの先へ歩んでいくことについて、アイドルはその目的になり得るか。
彼女たちは透明であることをかなぐり捨て、内輪だけの満足を捨てて、その輝きを誇示するように主張を始める。長い長い人生の中にある何かを探して、幼馴染に負けないように、置いていかれないように、ただ楽しいことを求めて。実のところ理由は様々かもしれないが、それでも、目的がバラバラでも、結束し、共に走り出す彼女たちの姿を、僕は羨ましいと思ったのだ。
# おわり
感想を書く時は何があったかではなく何を思ったかを書くようにしようと思いました。